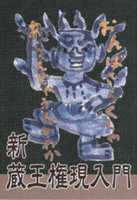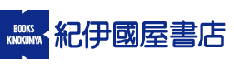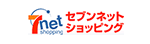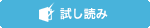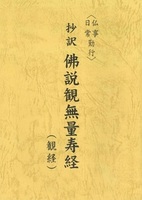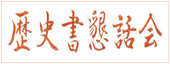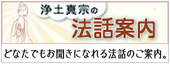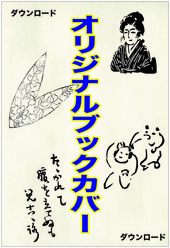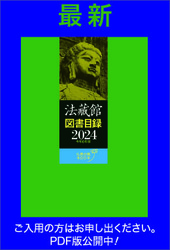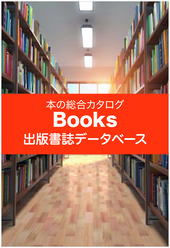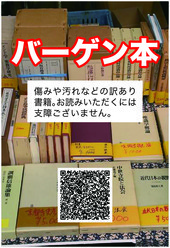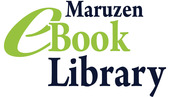話題の本【書評】(2024年9月~) - 2024.10.31
修験道という生き方 【新潮選書】
静かなブームの理由とは? 日本人の深層に生きる自然信仰を解き放つ。
修験道に目を向ける人が増えている。
彼らはなぜ山に惹きつけられるのか。
修験者として山中を歩くと何が見えてくるのか。
そもそも日本の信仰は自然とどう関わってきたのか。
日本仏教の源流とは――。
修験を代表する実践者であり理論家でもある二人の高僧と「里の思想家」内山節が、日本古来の山岳信仰の歴史と現在を語り尽くす。
修験道に目を向ける人が増えている。
彼らはなぜ山に惹きつけられるのか。
修験者として山中を歩くと何が見えてくるのか。
そもそも日本の信仰は自然とどう関わってきたのか。
日本仏教の源流とは――。
修験を代表する実践者であり理論家でもある二人の高僧と「里の思想家」内山節が、日本古来の山岳信仰の歴史と現在を語り尽くす。
序章 仏教と修験道
自然信仰と仏教、道教/文献のない信仰/開祖・役行者小角/仏教を受け入れた土着信仰/
民衆聖として/釈迦と仏教思想/華厳教学と大乗仏教/空海と中期密教/教団を持たない民衆信仰/
近世の修験道/講の誕生
第一章 修験道と公式仏教
教科書にはない仏教史/さまざまだった聖たち/整理しにくい存在/修験道的広がり
第二章 修験者という生き方
普通の人として/修験道と女性たち/奥駈への道程/山伏として生きる/
生きることが生み出す猥雑性に寄り添う/歩きこむという修行/仏縁のなかに生きている
第三章 つながりのなかを生きる
風土の記憶/三世救済の思想/すべてはつながっている/山頂は通らない
第四章 生活の中に入り込んだ信仰
ヒマラヤでの護摩行/精神の古層にある普遍/村の修験者たち/山伏と優婆塞信仰/
民衆信仰と国家制度/信仰をつくりだしたもの
第五章 教団のない宗教
記録に残らない庶民の信仰/「古修験」と役行者/公式の宗教と民衆の宗教/
修験道を支えた風土/江戸期の修験道
第六章 修験道と日本の近代化
神仏判然令と修験道廃止令/権現信仰/檀家のない寺/生き残った大峯信仰/
個人の時代へのまなざし
第七章 神仏を失いつつある時代
日本列島に暮らした人たちが帰属してきたもの/祈りが教えてくれるもの/
原発問題のとらえ方/詫びることを忘れた社会
第八章 悟りとは何か
本質としてのつながり/仏教と悟り/悟りと菩薩行/記憶のなかでの旅立ち/光に包まれた/
わし、死んでましてん
第九章 行足あって智目を知る
最古の信仰、現代の信仰/自力門、他力門/ハレの大切さ
自然信仰と仏教、道教/文献のない信仰/開祖・役行者小角/仏教を受け入れた土着信仰/
民衆聖として/釈迦と仏教思想/華厳教学と大乗仏教/空海と中期密教/教団を持たない民衆信仰/
近世の修験道/講の誕生
第一章 修験道と公式仏教
教科書にはない仏教史/さまざまだった聖たち/整理しにくい存在/修験道的広がり
第二章 修験者という生き方
普通の人として/修験道と女性たち/奥駈への道程/山伏として生きる/
生きることが生み出す猥雑性に寄り添う/歩きこむという修行/仏縁のなかに生きている
第三章 つながりのなかを生きる
風土の記憶/三世救済の思想/すべてはつながっている/山頂は通らない
第四章 生活の中に入り込んだ信仰
ヒマラヤでの護摩行/精神の古層にある普遍/村の修験者たち/山伏と優婆塞信仰/
民衆信仰と国家制度/信仰をつくりだしたもの
第五章 教団のない宗教
記録に残らない庶民の信仰/「古修験」と役行者/公式の宗教と民衆の宗教/
修験道を支えた風土/江戸期の修験道
第六章 修験道と日本の近代化
神仏判然令と修験道廃止令/権現信仰/檀家のない寺/生き残った大峯信仰/
個人の時代へのまなざし
第七章 神仏を失いつつある時代
日本列島に暮らした人たちが帰属してきたもの/祈りが教えてくれるもの/
原発問題のとらえ方/詫びることを忘れた社会
第八章 悟りとは何か
本質としてのつながり/仏教と悟り/悟りと菩薩行/記憶のなかでの旅立ち/光に包まれた/
わし、死んでましてん
第九章 行足あって智目を知る
最古の信仰、現代の信仰/自力門、他力門/ハレの大切さ
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る YONDEMILLとは
YONDEMILLとは お問い合わせ
お問い合わせ

 関連書籍
関連書籍