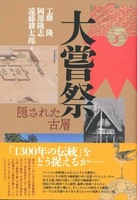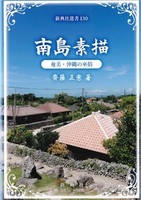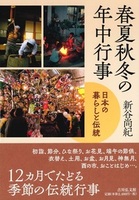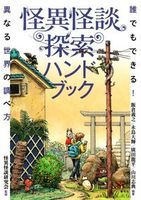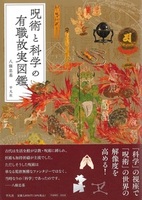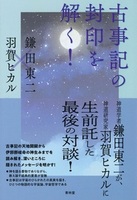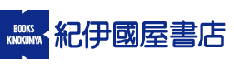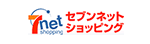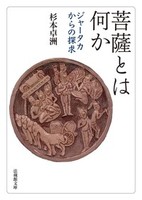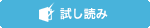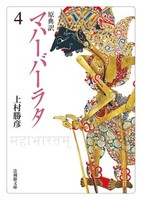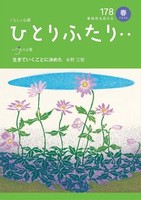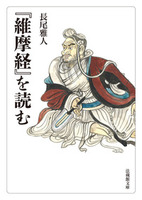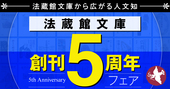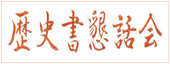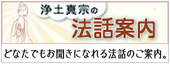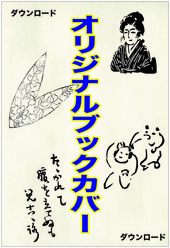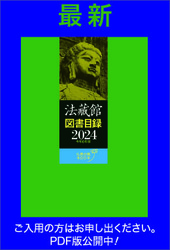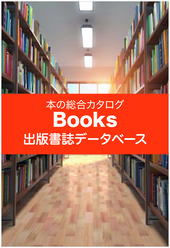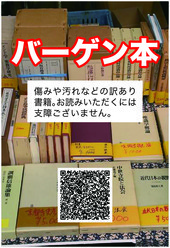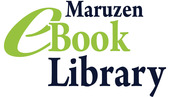話題の本【書評】(2024年9月~) - 2026.02.26
大嘗祭の本義
民俗学からみた大嘗祭
本書は折口信夫の「昭和三年講演筆記」を現代語訳したものである。
訳者の森田勇造は、以前から「日本の民族的、文化的源流を求めて」をテーマに、アジア東南部の稲作文化地帯諸民族の生活文化を踏査してきた。
今般の今上天皇譲位と新天皇の即位に際して、稲作文化としての〝大嘗祭〟に関心を持ち、明治以後の四代、東西八カ所の斎田地を探訪調査した。
そして、本年五月に『大嘗祭の起こりと神社信仰―大嘗祭の悠紀・主基斎田地を訪ねて―』の題名で出版することになった。
それにあたって必要な、昭和3年における折口信夫の講演録『大嘗祭の本義』を現代語訳した本書を同時に上梓する運びとなったのである。
2冊を合わせ読めば、日本にとって大変重要な大嘗祭の意味と意義がよく理解されるといえよう。
訳者の森田勇造は、以前から「日本の民族的、文化的源流を求めて」をテーマに、アジア東南部の稲作文化地帯諸民族の生活文化を踏査してきた。
今般の今上天皇譲位と新天皇の即位に際して、稲作文化としての〝大嘗祭〟に関心を持ち、明治以後の四代、東西八カ所の斎田地を探訪調査した。
そして、本年五月に『大嘗祭の起こりと神社信仰―大嘗祭の悠紀・主基斎田地を訪ねて―』の題名で出版することになった。
それにあたって必要な、昭和3年における折口信夫の講演録『大嘗祭の本義』を現代語訳した本書を同時に上梓する運びとなったのである。
2冊を合わせ読めば、日本にとって大変重要な大嘗祭の意味と意義がよく理解されるといえよう。
はじめに
一、にえまつりについて
二、まつりごととは
三、神嘗祭と新嘗祭
四、秋・冬・春祭りと鎮魂行事
五、宮廷の鎮魂式と物忌み
六、春の祭り
七、祝詞(祭りの儀式に唱えて祝福する言葉)
八、寿詞(天皇の長寿・繁栄を述べる祝いの言葉)
九、大嘗祭における御所の警護
十、風俗と語部について
十一、天皇様の禊ぎについて
十二、廻立殿のお湯
十三、天つ罪と国つ罪
十四、直会について
現代語訳を終えて
一、にえまつりについて
二、まつりごととは
三、神嘗祭と新嘗祭
四、秋・冬・春祭りと鎮魂行事
五、宮廷の鎮魂式と物忌み
六、春の祭り
七、祝詞(祭りの儀式に唱えて祝福する言葉)
八、寿詞(天皇の長寿・繁栄を述べる祝いの言葉)
九、大嘗祭における御所の警護
十、風俗と語部について
十一、天皇様の禊ぎについて
十二、廻立殿のお湯
十三、天つ罪と国つ罪
十四、直会について
現代語訳を終えて
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る YONDEMILLとは
YONDEMILLとは お問い合わせ
お問い合わせ
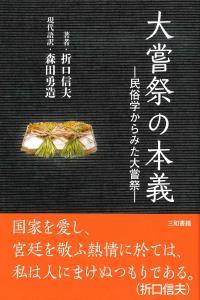
 関連書籍
関連書籍