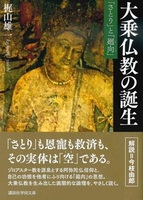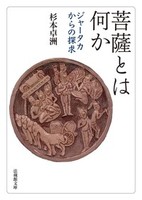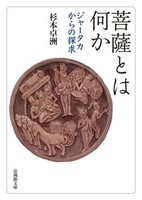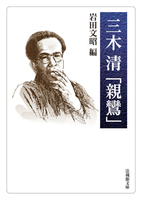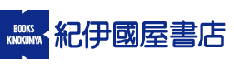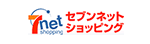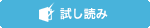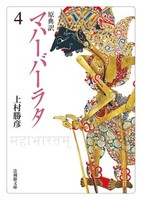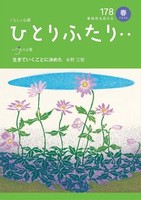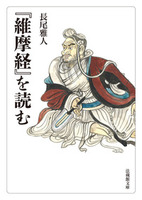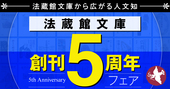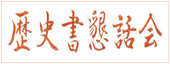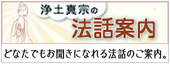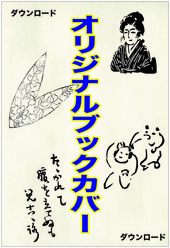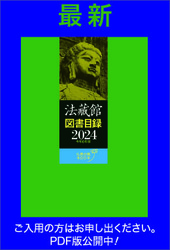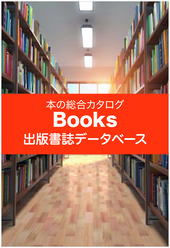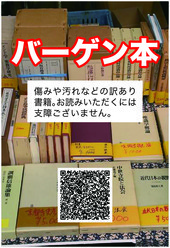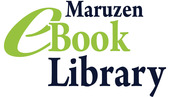話題の本【書評】(2024年9月~) - 2026.02.18
大乗仏教と小乗蔑視
声聞と声聞乗とはどう見られてきたか
インドにおける小乗蔑視の発生と受容、中国における小乗蔑視の受容と小乗批判の発生、そして、日本における小乗蔑視と小乗批判との受容――
大乗仏教が辿ってきた道を、大乗経から中観派、唯識派、最澄まで多彩な文献を用いて説きあかす。
小乗批判から生まれた、本来の大乗仏教と異なる「日本式大乗仏教」とは何か。
日本人の大乗仏教理解に再考を迫る。
一 本章のねらい/二 仏教の文献
三 仏教の聖者/四 仏教の三乗
五 大乗と小乗/六 乗という語
七 蔑視と批判/八 本書の構成
九 本章のまとめ
第一部 大乗仏教と声聞蔑視
第一章 声聞はいつ大慈大悲なき者となったか
一 本章のねらい/二 声聞は大悲を有しない
三 声聞は大慈大悲を有しない/四 本章のまとめ
第二章 声聞はいつ他者貢献なき者となったか
一 本章のねらい/二 声聞は他者貢献のために行ずる
三 声聞は他者貢献のためには行じない/四 本章のまとめ
第三章 声聞はいつ共に住めない者となったか
一 本章のねらい/二 菩薩は声聞と共に住む
三 菩薩は声聞と共に住まない/四 本章のまとめ
第四章 声聞はいつ尊敬されない者となったか
一 本章のねらい/二 菩薩は声聞を尊敬する
三 菩薩は声聞を尊敬しない/四 本章のまとめ
第二部 大乗仏教と声聞乗蔑視
第五章 部派の三蔵はいつ声聞蔵と呼ばれたか
一 本章のねらい/二 大乗経は菩薩蔵である
三 部派の三蔵は声聞蔵である/四 本章のまとめ
第六章 部派の経律はいつ声聞相応となったか
一 本章のねらい/二 部派の経は声聞相応である
三 部派の律は声聞相応である/四 本章のまとめ
第七章 声聞乗はいつ学ぶべきでなくなったか
一 本章のねらい/二 菩薩は声聞乗を学ぶ
三 菩薩は声聞乗を学ばない/四 本章のまとめ
第八章 波羅提木叉はいつ要されなくなったか
一 本章のねらい/二 菩薩は波羅提木叉を要する
三 菩薩は波羅提木叉を要しない/四 本章のまとめ
結 章 声聞批判・声聞乗批判はいつ生じたか
一 本章のねらい/二 インドにおける声聞蔑視・声聞乗蔑視の受容
三 中国における声聞蔑視・声聞乗蔑視の受容
四 日本における声聞蔑視・声聞乗蔑視の受容
五 中国における声聞批判・声聞乗批判の発生と日本におけるその受容
六 日本式大乗仏教の形成/七 本来の大乗仏教と日本式大乗仏教との区別
八 本章のまとめ
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る YONDEMILLとは
YONDEMILLとは お問い合わせ
お問い合わせ
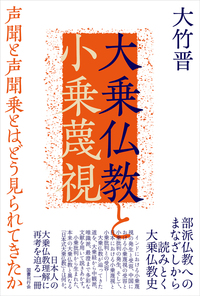
 関連書籍
関連書籍