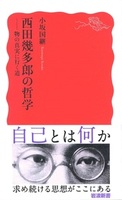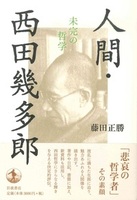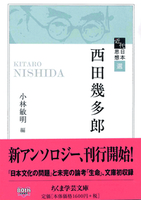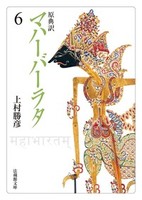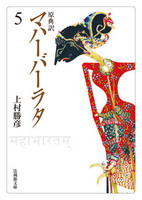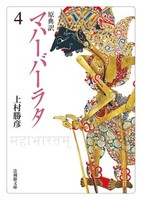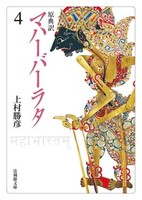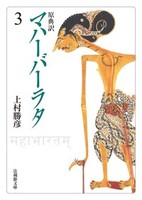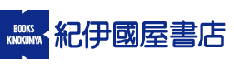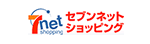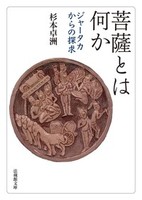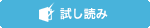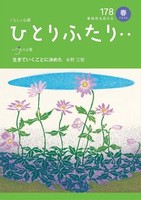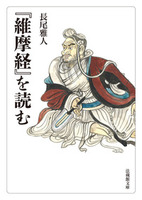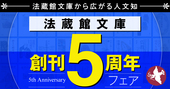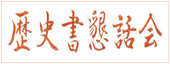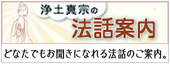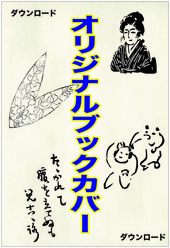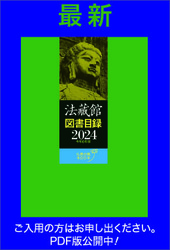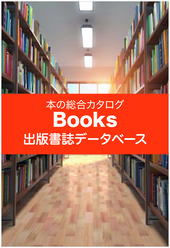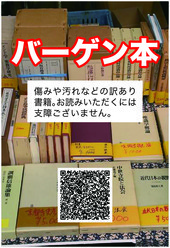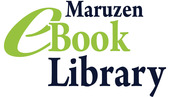新刊チラシ(2026年度刊行分) - 2026.02.13
ドイツ観念論と京都学派の哲学
ケルン大学・テュービンゲン大学講義録
プロローグ 日本哲学の世界環境――思想進化史のガラパゴス現象
1 変化しつつある日本哲学の世界環境
2 思想進化史のガラパゴス現象――孤立性と画期性
3 「日本哲学」の新たな位置図へ
補論 「真理像の時代」
序 章 ドイツ観念論と京都学派の六つのファセット
1 誰が「ドイツ観念論」や「京都学派」の名称を言い出したか
2 四つの哲学潮流と、第五の潮流としての京都学派
3 ファセットとしての六つのテーマ
第Ⅰ部 歴 史
第1章 革命の時代のドイツ哲学界と東アジアの歴史観
1 ドイツ観念論の時代の「三つの傾向」
2 ナポレオンとヘーゲルの一回だけの「交差」
3 「宗教改革」と「ドイツ観念論」のドイツ的な由来
4 フスの時代とルターの時代とのちがい
5 「新時代」の準備としての啓蒙主義
6 ウイーン体制と三月前期
7 ドイツと日本の近代化の並行性
8 東アジアの歴史観のポテンシャル
第2章 「神」の歴史か、「絶対無」の歴史か
1 新史料「大島メモ」の発見
2 カントの歴史思想――自然とのアナロジー
3 フィヒテの歴史思想――絶対自我の歴史原理
4 シェリングの歴史思想――「神的な啓示」としての歴史
5 ヘーゲルの歴史思想――「絶対精神」の歴史
6 京都学派の「絶対無」の歴史理念
第Ⅱ部 自 然
第3章 東西の自然概念
1 「自然」、「自己」、「自我」に含まれる日本語の「自」
2 「自然法」か「実定法」か――フィヒテの女性観・結婚観と連関して
3 カントにおける「自然」
4 ヘルダーリンにおける「自然」
第4章 自然哲学と「絶対自我」
1 日本語の「我」(自我、私)
2 フィヒテの「知識学」と「絶対自我」
3 シェリングの自然哲学
4 ヘーゲルの自然哲学
5 自然哲学と自然科学の新たな関係へ
6 京都学派の「自然」とドイツ観念論の「自然」の遠近さ
第5章 〔特講〕デカルト・スピノザ・ライプニッツの「自然」
1 中世と近世の二方向を向く「ヤヌスの首」デカルト
2 コペルニクスとケプラーの場合
3 スピノザとライプニッツによるデカルト超克
4 「機械論的世界観」から「生命論的世界観」への近代的展開
第Ⅲ部 芸 術
第6章 ロマン主義とカント美学
1 「芸術」――自然の模倣か、芸術意欲による創作か
2 「新旧論争」
3 芸術考察の三つの領域
4 初期ロマン主義
5 ロマン主義のさまざまな領域
6 カント美学――「美的判断力」の考察
7 種々のイロニー概念
8 京都学派の芸術理解、その1――「芸術」か「芸道」か
第7章 ヘーゲルの「芸術の過去性」テーゼ
1 カントの「自然美」とヘーゲルの「芸術美」
2 シェリングの芸術哲学、その1――美的直観
3 ヘーゲルの芸術哲学――「芸術の過去性」テーゼとその射程
4 シェリングの芸術哲学、その2――「異教的なもの」としての芸術
5 京都学派の芸術理解、その2――西田幾多郎の場合
第Ⅳ部 法
第8章 カント、フィヒテ、ヘーゲル、そして西谷啓治
1 ドイツ語の「法」と日本語の「法」
2 ドイツ観念論の法哲学
3 カントの法哲学――汝なすべし
4 フィヒテの法哲学――自然法とその帰結
5 ヘーゲルの法哲学、その1――「欲望/需要の体系」としての市民社会
6 ラートブルッフ「五分間の法哲学」
7 京都学派の法思想、その1――西谷啓治「国家の無我性」という考え
第9章 国家と社会の弁証法
1 ヘーゲルの法哲学、その2
2 京都学派の法思想、その2
第Ⅴ部 知
第10章 物自体という壁
1 「何かを知る」とはどういうことか――「チャットGPT」断想
2 東洋思想における「不知の知」
3 西洋哲学の中にも顔を出す「絶対無」
4 カント――「不可知の物自体」が招くジレンマ
5 カント以後の思想家群像
6 西田哲学における「知」
第11章 絶対知をめぐる「巨人の戦い」
1 論争書簡、論争著述
2 フィヒテとシェリングの共通点と相違点
3 フィヒテの絶対知
4 シェリングの絶対知
5 ヘーゲルの絶対知
6 西谷啓治の「般若知」
第Ⅵ部 宗 教
第12章 ニヒリズムの胎動
1 絶対者の現前の場としての宗教
2 ドイツ観念論の宗教の歴史的背景
3 絶対者と絶対無(部分的反復)
4 フィヒテにおけるニヒリズムの意味
5 西田の「宗教的世界観」――田辺の西田批判、その2
第13章 「無底」――ドイツ観念論と京都学派の邂逅地点
1 西谷啓治の「自由論」和訳がドイツ語版の編纂史に投じた一石
2 ハイデッガーのシェリング「自由論」解釈――「無底」を迂回する理由
3 西谷における神秘主義の自己化(Aneignung)と奪自己化(Enteignung)
4 西谷テーゼ「絶対空が真の無底である」
エピローグ ヘーゲル哲学と西田哲学の切り結び点
1 西田の「私の立場」とは何であったか
2 西田は「ヘーゲル弁証法」をどう再構成したのか
3 西田の立場から見たヘーゲルとの切り結び点
あとがき 鎮魂曲の想を兼ねて
索 引
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る YONDEMILLとは
YONDEMILLとは お問い合わせ
お問い合わせ
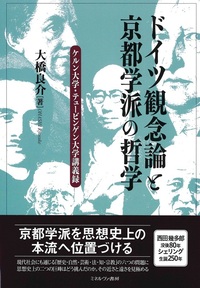
 関連書籍
関連書籍